🕰️ ① 岩田屋中心の「天神四つ角」時代(〜1970年代前半)
- 戦後〜1970年代前半:天神はまだ「西鉄福岡駅前=岩田屋前交差点(四つ角)」が中心。
- 西鉄の地上駅と岩田屋が象徴的で、福ビル・西鉄名店街・天神コア(1976年開業)などが立ち並び、いわゆる“岩田屋の街”だった。
- この頃はまだ、北(長浜方面)も南(春吉方面)も未開発。
- 商業と交通の結節点として、天神の都市機能が形成され始めた時期。
🏙️ ② 北天神への拡張と若者文化の萌芽(1970年代後半〜1980年代)
- 1971年:「ショッパーズプラザ福岡」(現イオンショッパーズ福岡)開業。
- 1974年:「フタタ本店」開業。
→ これがきっかけで「北天神」という概念が生まれ、天神の商圏が北へ広がる。 - 1980年代に入ると、北天神〜親不孝通り(現・親富孝通り)が若者文化の発信地となる。
→ 予備校が多く、浪人生や学生が集う街として「親不孝通り」と呼ばれるようになった。
→ 同時期にディスコブームが到来し、この界隈にディスコ・ナイトクラブが集中。
→ 勉強・遊びの両方の“若者の夜の街”として一世を風靡。
🚇 ③ 天神地下街の誕生(1976〜1981年)
- 1976年:天神地下街(北側)開業。
- 1981年:南側まで延伸し全線開通(全長590m)。
→ 地下で岩田屋〜ショッパーズ〜南天神がつながり、天神全体の一体感が生まれる。 - 地下街の完成により、天神は**「全天候型ショッピング都市」**として全国的に注目される。
- 天神の歩行動線が地上から地下へ移り、都市としてのスケールアップが始まる。
👗 ④ 若年層ファッション文化の黄金期(1976〜2000年代)
- 1976年:「天神コア」開業
→ 高校生〜20代前半のファッション拠点。 - 1982年:「天神ビブレ」開業
→ コアよりカジュアルで、ストリート・音楽系カルチャーの中心。 - 1989年:「イムズ(IMS)」開業
→ 大学生〜20代後半向け。都会的で洗練されたブランド群。
→ コア・ビブレより少し上の層を取り込み、天神のファッション層を三層構造化。 - 1990〜2000年代初頭:
→ コア+ビブレ+イムズが若者文化を牽引。
→ 天神全体が“世代別ショッピング街”として機能。
🏬 ⑤ 南天神への拡張(1990年代後半)
- 1997年:「大丸福岡天神店(エルガーラ)」開業。
- 渡辺通・春吉方面まで商圏が拡大し、「天神南」という呼称が定着。
- この頃から、中央区南部(警固・薬院)も“都心生活圏”に含まれるようになる。
- 都心居住・都市型ライフスタイルという概念が生まれ、住む都心としての天神が形成されていく。
👕 ⑥ 若者文化の南西進出:大名・西通りブーム(1990年代〜2000年代初頭)
- 1990年代〜2000年代初頭:
→ 若者向けのショップ(古着、セレクト、カフェ)や飲食店が急増。
→ 大名・西通りエリアが「サブカルチャー・ファッション・雑貨」の集積地となる。 - 九州中の若者が集まり、ストリートファッションと音楽・カフェ文化が融合。
- 夜の親不孝通りに対して、昼の大名・西通りが“新しい若者文化の聖地”となる。
- これにより、天神の商業・文化の重心が**「北の親不孝」→「西の大名」へとシフト**。
🏢 ⑦ 関東系百貨店の進出と再編(2000年前後)
- 2004年:「福岡三越」開業(ソラリアプラザ上層階に本格展開)。
→ 実質的には2000年代初頭に、岩田屋・大丸に加え、**首都圏系百貨店(三越)**が並ぶ構図に。 - 2005年:「岩田屋」と「三越」が経営統合(IMHホールディングス発足)。
→ 福岡天神は「地場百貨店と全国資本の融合型」商業地に変化。
🚄 ⑧再開発が変えた「県外客の動線」
- 2011年:JR博多シティ開業(アミュプラザ+阪急+T・ジョイ+東急ハンズ)
→ 新幹線・空港・地下鉄が全て直結。 - 県外客は、博多駅に降りた瞬間から「百貨店・シネコン・レストラン・土産」がすべて揃う。
→ 天神一極化へに変化。 - 福岡空港から地下鉄で5分で着くため、日帰り出張・観光でも時間効率が圧倒的。
🏗️ ⑨ 現代:天神ビッグバンと再中心化(2010年代〜現在)
- 「天神ビッグバン」で福ビル・天神コア・岩田屋新館跡などが再開発中。
- 天神交差点(岩田屋前)が再び“核”となり、
「北天神」「南天神」「西通り・大名」を包含する**“中央天神=再統合期”**に入っている。 - 現代の天神は、かつての百貨店中心から、商業・文化・居住・観光の複合都心へ進化。→ 天神全体が“ハイブランド寄り・観光商業寄り”へシフト。

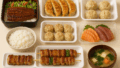

コメント